313 城ヶ崎=氷見市阿尾(富山県)ここが県内で2つしかない岬のひとつで阿尾城の跡が… [岬めぐり]
近頃、若いもんの間で、戦国武将が人気になっているのだという。なんでもいい。若い人が歴史に興味を持つのは、おおいに歓迎し奨励すべきことだ。
越後路を電車で走っていると、やたら上杉謙信のなにやかやが目につくし、金沢はいうにおよばす能登へ行くとそこではいまだに“利家とまつ”の等身大の看板が現役で活躍していたりする。しかし、富山ではそういう郷土の歴史スターをもたない。
いや、富山城主としては、戦国中期までは織田信長の重臣の一人として佐々成政がいた。だが、彼は戦国武将としてのキャリアをまっとうしたとはいえなかったためか、郷土の英雄・英傑にはなれなかったようだ。
唯一有名なのは、反豊臣の立場になって上杉と前田に挟まれて身動きできなくなった彼が、冬の針ノ木岳のザラ峠を越えて、家康に救援を求めたエピソードで、これはハンニバルのアルプス越えというイメージと重なってか、あるいは登山者の間で語り継がれてきたためかであろう。


氷見の城ヶ崎は、その佐々成政に従っていた菊池氏の居城であった阿尾城があったところである。菊池氏は前田方へ寝返り、そのおかげで前田配下の小城主となって生き延びるが、江戸慶長年間には廃城になっている。阿尾城は、海に張り出した小高い岬の上に構えられた小城で、どうやら富山湾の海上警備にその役割があったように思える。白く高く垂直(というより、ここは オーバーハングだな)の崖は、いわきの岬を思い出させる。現在は、二つの神社とともに史跡城跡公園として保存されている。


城跡の北側には住宅地が密集しているが、ここには温泉もありホテルらしい大きな建物も見える。
富山名物の「ますのすし」を買ってきたので、大きな老木と夏草に埋もれたその城跡に腰を降ろし、富山湾のほうを眺めながら、いただくことに。ポコンと浮かぶ小島は、氷見港の沖にある唐島である。遠くの左の辺りが、富山県の2つしかない岬のもうひとつ、生地鼻になるはずで、実はここへくる前によってきたかったのだが、ダイヤの都合がうまくなく、あきらめた。

富山というところは、でんでんむしにとってはあまりなじみがないところである。初めてきたのは、まだ10代の終わり頃のことで、北アルプス表銀座の初心者コースを終えた後、唐松越えに挑戦し、やっとの思いで黒部の祖母谷に降り、翌日欅平から関西電力のトロッコに乗って宇奈月経由で富山に降りたことがあるくらいだ。だからここ氷見市は初めてだった。
氷見といえばブリとか、富山湾といえばホタルイカに蜃気楼という、社会科的なことのいくつかは知っているとはいえ、それらが通りすがりにちらちらするというものでは、もちろんない。
ここへくる前、氷見の中心部を、脇へ行くバス停を探してうろうろしていると、ちらちらしたのは「氷見うどん」の幟だけだった。



脇というのは、氷見市の北端にある小さな町である。高岡から、加越能バスが脇まで運行しているので、その路線でここまでやってきた。
高岡からは、JRの氷見線もあり、このほうが海岸線を走るので、どちらかといえば160号線で内陸の町を結びながら走るバスよりいいのだが、めったに走らないのでこれには乗れずじまいだった。阿尾で次のバスを待ち、脇へ向かう。
▼国土地理院 「地理院地図」
36度52分46.20秒 136度59分31.75秒
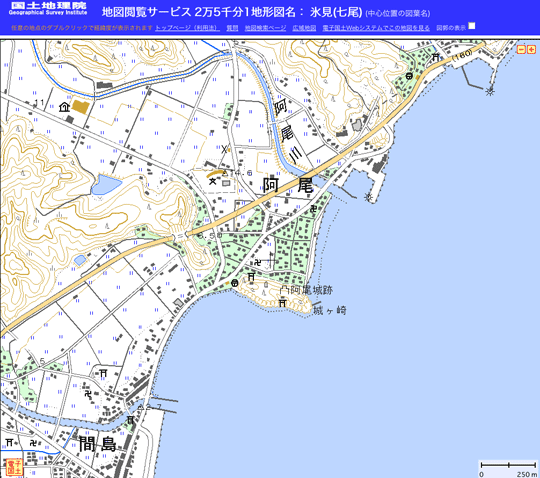
 北越地方(2008/09/05 訪問)
北越地方(2008/09/05 訪問)


越後路を電車で走っていると、やたら上杉謙信のなにやかやが目につくし、金沢はいうにおよばす能登へ行くとそこではいまだに“利家とまつ”の等身大の看板が現役で活躍していたりする。しかし、富山ではそういう郷土の歴史スターをもたない。
いや、富山城主としては、戦国中期までは織田信長の重臣の一人として佐々成政がいた。だが、彼は戦国武将としてのキャリアをまっとうしたとはいえなかったためか、郷土の英雄・英傑にはなれなかったようだ。
唯一有名なのは、反豊臣の立場になって上杉と前田に挟まれて身動きできなくなった彼が、冬の針ノ木岳のザラ峠を越えて、家康に救援を求めたエピソードで、これはハンニバルのアルプス越えというイメージと重なってか、あるいは登山者の間で語り継がれてきたためかであろう。


氷見の城ヶ崎は、その佐々成政に従っていた菊池氏の居城であった阿尾城があったところである。菊池氏は前田方へ寝返り、そのおかげで前田配下の小城主となって生き延びるが、江戸慶長年間には廃城になっている。阿尾城は、海に張り出した小高い岬の上に構えられた小城で、どうやら富山湾の海上警備にその役割があったように思える。白く高く垂直(というより、ここは オーバーハングだな)の崖は、いわきの岬を思い出させる。現在は、二つの神社とともに史跡城跡公園として保存されている。


城跡の北側には住宅地が密集しているが、ここには温泉もありホテルらしい大きな建物も見える。
富山名物の「ますのすし」を買ってきたので、大きな老木と夏草に埋もれたその城跡に腰を降ろし、富山湾のほうを眺めながら、いただくことに。ポコンと浮かぶ小島は、氷見港の沖にある唐島である。遠くの左の辺りが、富山県の2つしかない岬のもうひとつ、生地鼻になるはずで、実はここへくる前によってきたかったのだが、ダイヤの都合がうまくなく、あきらめた。

富山というところは、でんでんむしにとってはあまりなじみがないところである。初めてきたのは、まだ10代の終わり頃のことで、北アルプス表銀座の初心者コースを終えた後、唐松越えに挑戦し、やっとの思いで黒部の祖母谷に降り、翌日欅平から関西電力のトロッコに乗って宇奈月経由で富山に降りたことがあるくらいだ。だからここ氷見市は初めてだった。
氷見といえばブリとか、富山湾といえばホタルイカに蜃気楼という、社会科的なことのいくつかは知っているとはいえ、それらが通りすがりにちらちらするというものでは、もちろんない。
ここへくる前、氷見の中心部を、脇へ行くバス停を探してうろうろしていると、ちらちらしたのは「氷見うどん」の幟だけだった。



脇というのは、氷見市の北端にある小さな町である。高岡から、加越能バスが脇まで運行しているので、その路線でここまでやってきた。
高岡からは、JRの氷見線もあり、このほうが海岸線を走るので、どちらかといえば160号線で内陸の町を結びながら走るバスよりいいのだが、めったに走らないのでこれには乗れずじまいだった。阿尾で次のバスを待ち、脇へ向かう。
▼国土地理院 「地理院地図」
36度52分46.20秒 136度59分31.75秒
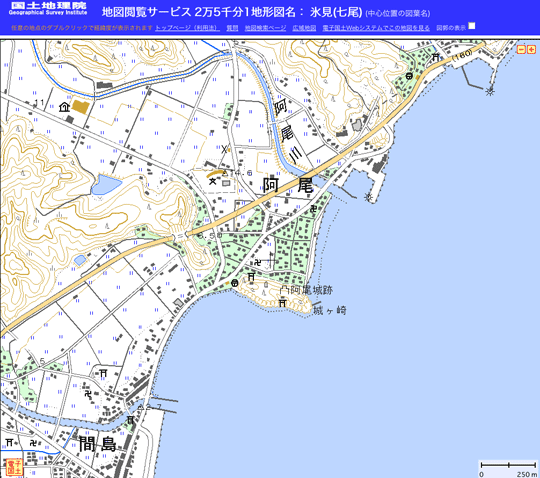
タグ:富山県


 番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)
番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)





 2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
これぞ岬というか、岬の標本になりそうな絵柄ですね。二つしかない岬のひとつが正調の姿をとどめているのは健気な感じです。
恥ずかしながら拙者、富山県と石川県がごっちゃになっていて、もっと外海に面しているように思っていました。地図を見直して、あらためて「たった二つの岬」の事情がわかりました。
話は変わりますが、けさの朝日で「日本鉄道旅行地図帳」(新潮社)の広告を見ました。先刻ご承知でせうが、ありやいい企画ですね。わりと廉価で楽しめそうに思いました。
by knaito57 (2008-09-18 20:18)
@もちろん先刻ショウチノスケで、シンチョウシャがいよいよここへ目をつけたかと、感動しましたね。さっそく買おうと思ったのだけど、現物を見て、あるいは監修者がこうきたかと、とりあえずやめたの。
まあ、そんなに高価というものでもないんで、文句なしに買ってもいいんだけど…。
でも、へそ曲がりの地図マニアとしては、この程度でマンマとムコウの思惑にはまってしまうのが、シャクに障るのでね。まだ…。
by dendenmushi (2008-09-19 07:53)