442 館ヶ崎=宮古市日立浜町(岩手県)たいせつなことは「?」と「!」 [岬めぐり]
「浄土ヶ浜」は、三陸を代表する観光地で、館ヶ崎はその南端に位置する岬である。
この岬の南面は、宮古港からも眺められたが、浄土ヶ浜の回遊コースに入ると、高い展望台からここがよく見通せる。
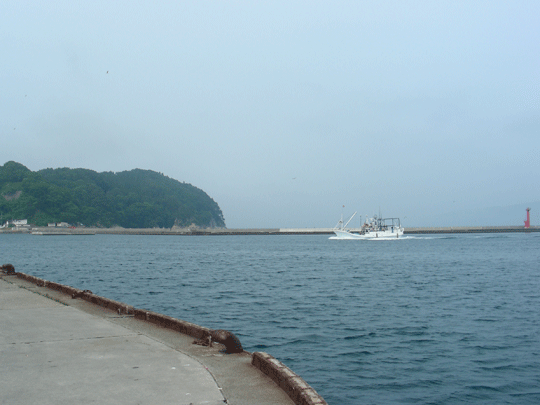
この展望台は、昔とちっとも変わっていない。そこから見えている景色も、まったく変わっていない。断崖絶壁は、リアス式海岸の特徴のひとつと言えるが、ここの高さは30メートル強といったところ。リアス式の特徴を備えた地形は、全国各地にあるが、これが本場、三陸海岸の岬だ。観光地にせよ世界遺産にせよ、その効用には人々の注目の中において、その姿を変わらず保つ、ということがあるのかもしれない。
館ヶ崎では、岬の内側の入江が、遊覧船の発着場になっている。遠くに霞んでいるのは、重茂(おもえ)半島(結構大きな半島なのに、この名は地図にはでてこないが)北端の閉伊崎である。

「リアス式海岸」という言葉は、まずたいていの人がこどもの頃学校の授業で習って、死ぬまで忘れないことのひとつであろう。
こういう知っていても知らなくてもまったく関係がないような、さして重大事でもなく、人間が生きるために必須とも思えない雑多な知識を、幅広くたくさん詰め込むのが教育だとしたら、それは一定の成果をあげている。
若い頃には、実生活には直接役に立たない学校の授業が、無意味なものに思えることもあったが、歳をとってくると、そうではないのだと思い至る。
これはでんでんむしの持論だが、仕事でもなんでも、人間なにをやるうえでも、最も肝心なことは、「?」と「!」である。もちろん、「岬めぐり」でも…。
“義務教育の基本的な目的は、こどもたちに「?」と「!」のノウハウを教え、身に付けさせることではないのか”というのは、でんでんむしの勝手な解釈に過ぎない。
岬ができる要因は、ごく簡単にいってしまえば、「隆起」と「沈降」が主なものだろうが、三陸のリアス式海岸は、宮古から北は隆起、そして、宮古から南は沈降によるものだと考えてよい。
「隆起」の場合は、陸地の全体や一部が持ち上がって、岬として残ったり、断崖絶壁ができたり、テーブル状の台地ができたりする。
「沈降」の場合は、陸地だったところが沈んで、高いところの尾根や岬や小島が残り、谷が溺れて入江になり、ギザギザの海岸線をつくる。
日本地図でこの三陸海岸をみれば、なるほど宮古から南部はノコギリの刃のようにギザギザだが、北部はさほどではない。このため、ギザギザの南部だけがリアス式海岸であり、その北限が宮古だと、勘違いされている向きもあるようだが、それは違うのである。
現に、宮古駅から北へ久慈駅までを結んで走る三陸鉄道は、「北リアス線」と呼ばれている。
今回の第一次三陸岬めぐり計画では、この北リアス線に沿って宮古から久慈まで行き、また引返してきて往復する計画だが、レンタカーなので、電車には乗らない。
39度38分48.45秒 141度58分56.14秒
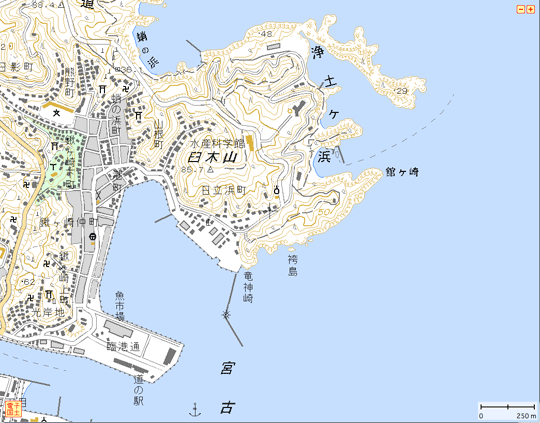


 番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)
番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)





 2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
宮古とは懐かしいのう……ラジオ放送の気象情報を思い起こす。未踏の地ながら、たしかに彼の地はいつも「風力3」でござった。
お陰様とはいえ、けふの画像から直ちに「宮城県松島シリーズ」を連想する拙者の素養・眼力も相当なもの(自賛)、ふむ、凹凸多い急峻で、ちゃんと松も生えておる。
手許の字引によると「?」は「はて面妖な、不可思議千万」、「!」は「ややっ。これは仰天、驚き桃の木山椒の木」とある。それはさておき、当地流山電鉄に鰭(ひれ)ヶ崎という駅があってな、何ゆえ海から遠いこの地に鰭とか崎かと、いまだに「?」でござる。嗚呼、不可解なり!
by dotenoueno-okura (2009-07-07 10:59)
@「?」は、疑問をもつこと、「!」は、ユリイカ! わかったぞという喜び、ですね。
海でも岬でもないのに「なんとか崎」という地名があることについては、いずれ書かなければならないと考えています。
このなかには、もともと海とは関係がないものと、その昔の記憶を留めたものと、二通りあると想像されます。
流山電鉄の鰭ヶ崎は、「ひれ」なのでなにやら海とも関係がありそうだが…?? !!
by dendenmushi (2009-07-09 05:43)