465 鵜石鼻=倉敷市児島唐琴(岡山県)ナゾの「唐琴警鐘台」 [岬めぐり]
「唐琴」というからには、その地名の由来に関するエピソードのひとつもあるかと期待するが、どうやらそういうものもなさそうだ。中国の琴や箏にくわしくもないが、形からきているとすれば、200メートルほどの山に囲まれた半月形の地形自体が、唐琴の由来なのかもとも思えたりする。
海岸に沿うわずかな平地であったところにできている唐琴集落は、東は王子ヶ岳の山裾が海に落ち、西は砂浜の海岸だったらしいので、両側には人家もなく、ほんとにここだけに固まって人が住んでいたようだ。


鵜石鼻は、浜にせりだした、小さな丘の先端であったようだ。
今では、それとはっきりわかるのは、長く海に突き出している堤防だけが、岬の存在をあえて強調しているかのようである。
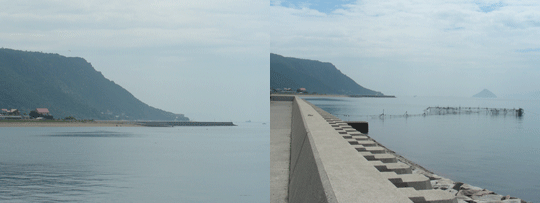
この岬とそれを主張するいまや唯一の堤防は、田の口の埋立地からも見えていた。この写真だと、大きな山から落ちる先端が、鵜石鼻のように見えるが、この山は鵜石鼻から3キロも東の位置にある、王子ヶ岳・新割山である。
唐琴の東西は、いずれもかつてはその海岸美を競ったことであろう。
だが、一帯は広範囲にわたって、“公共事業”といやつが盛んに進められている最中で、見た限りでは、この浜がどう「保全」されようとしているのか、よくわからない。

鵜石鼻を保全しようとは、誰も考えなかったようで、すぐ上には新しい住宅が聳え、すぐ横には古くからの住宅が並んでいる。


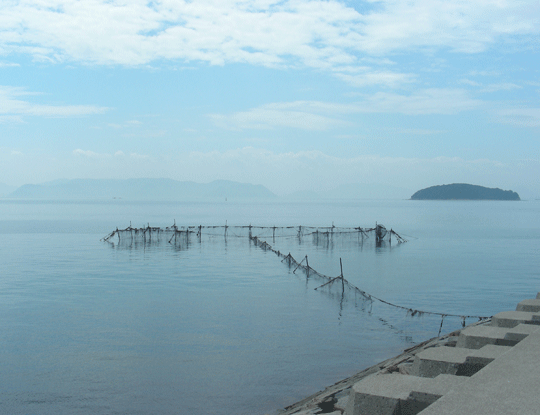
そうだ。瀬戸大橋と久須美鼻も、この岬から見えているので、まあ、いちおう記録しておかなければ。それと、この定置網の向うの平べったい島は、堅場島。
海岸から、人家の間の細い路地を抜けて、再び430号線に戻ると、降りた場所とは違う「唐琴警鐘台」というバス停に出た。
唐琴警鐘台…とな。
それはいったいなんだろう。火の見やぐらのようなものか。警鐘を鳴らすとは、なんの警鐘なのだろう。
あたりをいろうろしてみても、なんにもわからない。そのうちバスが来てしまう。下電バスの時刻表を見る通り、朝8時から夕方5時までの間の、たった一本しかないバスなので、これを逃すわけにはいかない。
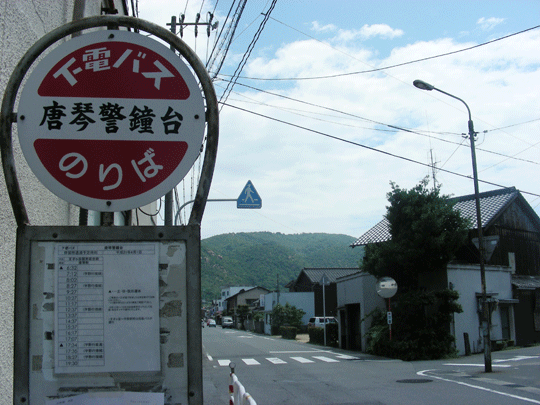
どうも気になるので、たまにしかやらないことだが、これを書く前にネットで検索してみた。
実を言えば、以前からこの「検索」には多々疑問があった。
でんでんむしは、検索にはもっぱらYahoo!を使う。Googleのほうがいいというひとが多いが、これはやたら多く検索するするだけで、メリットがないと思っている。
たとえば、「唐琴警鐘台」で検索すると、Yahoo!では5ページしか拾わないが、Googleでは「 唐琴警鐘台 に一致する日本語のページ 約 1,340 件」として15ページにわたって麗々しく表示する。ところが、そのほとんどは「唐琴警鐘台」とは、なんの関係もなく、ただ単に「警鐘」の二文字を含んだページを拾っているだけである。
検索の問題は、これからである。
でんでんむしが岬めぐりで初めての土地に行くとき、ホテルを探さなければならない。これが、少し町からはずれると、岬はあってもホテルはないというところがほとんどだ。
そこで付近の宿泊できる場所を検索しようとすると、いわゆるビジネスとして旅館・ホテルの斡旋をする「じゃらん」のような専門サイトのページばかりが出てくる。これは自分とこの契約ホテルしか出てこないうえに、検索ノミネートしてくる幅が広すぎる。
つまり、たとえで言うと、こちらは茨城の海岸のホテルを探そうとしているのに、箱根の山の中のホテルがお勧めですよ、と平気で言うようなものだ。およそ、人をバカにしておる。
不動産関係の検索にも似たようなことがあって、ストレートに物件に行き当たることは少なく、たいていはまずは不動産業者のページへどうぞと誘導されるが、そこに探している物件があるとは限らない。
さて、問題の「唐琴警鐘台」。
これが、Yahoo!で検索したところ、そのほとんどすべてが「唐琴警鐘台バス停下車徒歩5分」といった、不動産や施設の道しるべとして記載されたものだけ。それについてのまともな情報は、皆無だった。
「唐琴警鐘台」は、何に警鐘を鳴らそうとしているのだろうか。ナゾである。
この件について、問い合わせていた倉敷市役所児島支所から、返事とともに写真と所在図まで、送っていただいたので、それを追加しておこう。ただし、所在図は「バス停から北の山のほうに若干登ったところ」ということで。ありがとうございました。(2009/09/11追記)
「唐琴警鐘台とは,唐琴地区にある旧消防機庫の隣に設置された火の見櫓のことだそうです。
場所および写真を別添で送付させていただきますので,よろしくお願いします。児島支所総務課(09/09)」

やっぱり火の見やぐらだったんだ。それにしても、返事かきたこの日は09/09(救急の日)!? 関係ないですね。
▼国土地理院 「地理院地図」
34度28分1.93秒 133度51分34.06秒
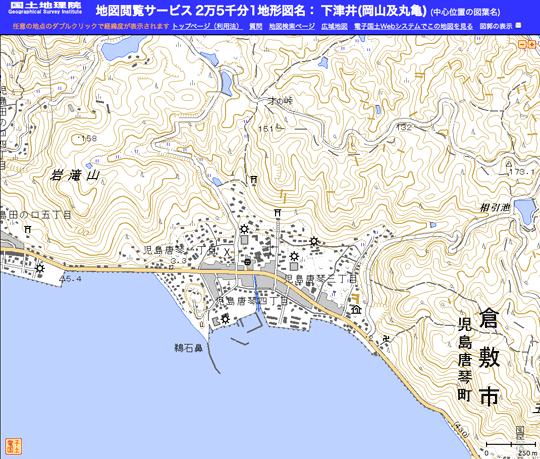
 中国地方(2009/08/13 訪問)
中国地方(2009/08/13 訪問)


海岸に沿うわずかな平地であったところにできている唐琴集落は、東は王子ヶ岳の山裾が海に落ち、西は砂浜の海岸だったらしいので、両側には人家もなく、ほんとにここだけに固まって人が住んでいたようだ。


鵜石鼻は、浜にせりだした、小さな丘の先端であったようだ。
今では、それとはっきりわかるのは、長く海に突き出している堤防だけが、岬の存在をあえて強調しているかのようである。
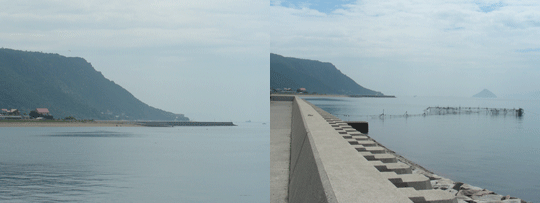
この岬とそれを主張するいまや唯一の堤防は、田の口の埋立地からも見えていた。この写真だと、大きな山から落ちる先端が、鵜石鼻のように見えるが、この山は鵜石鼻から3キロも東の位置にある、王子ヶ岳・新割山である。
唐琴の東西は、いずれもかつてはその海岸美を競ったことであろう。
だが、一帯は広範囲にわたって、“公共事業”といやつが盛んに進められている最中で、見た限りでは、この浜がどう「保全」されようとしているのか、よくわからない。

鵜石鼻を保全しようとは、誰も考えなかったようで、すぐ上には新しい住宅が聳え、すぐ横には古くからの住宅が並んでいる。


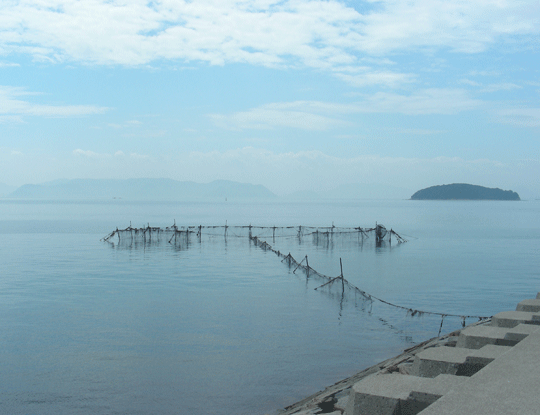
そうだ。瀬戸大橋と久須美鼻も、この岬から見えているので、まあ、いちおう記録しておかなければ。それと、この定置網の向うの平べったい島は、堅場島。
海岸から、人家の間の細い路地を抜けて、再び430号線に戻ると、降りた場所とは違う「唐琴警鐘台」というバス停に出た。
唐琴警鐘台…とな。
それはいったいなんだろう。火の見やぐらのようなものか。警鐘を鳴らすとは、なんの警鐘なのだろう。
あたりをいろうろしてみても、なんにもわからない。そのうちバスが来てしまう。下電バスの時刻表を見る通り、朝8時から夕方5時までの間の、たった一本しかないバスなので、これを逃すわけにはいかない。
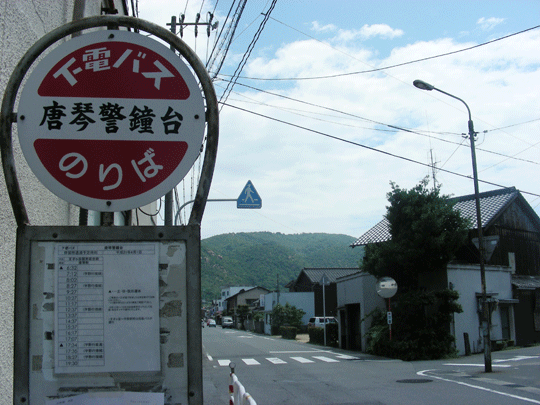
どうも気になるので、たまにしかやらないことだが、これを書く前にネットで検索してみた。
実を言えば、以前からこの「検索」には多々疑問があった。
でんでんむしは、検索にはもっぱらYahoo!を使う。Googleのほうがいいというひとが多いが、これはやたら多く検索するするだけで、メリットがないと思っている。
たとえば、「唐琴警鐘台」で検索すると、Yahoo!では5ページしか拾わないが、Googleでは「 唐琴警鐘台 に一致する日本語のページ 約 1,340 件」として15ページにわたって麗々しく表示する。ところが、そのほとんどは「唐琴警鐘台」とは、なんの関係もなく、ただ単に「警鐘」の二文字を含んだページを拾っているだけである。
検索の問題は、これからである。
でんでんむしが岬めぐりで初めての土地に行くとき、ホテルを探さなければならない。これが、少し町からはずれると、岬はあってもホテルはないというところがほとんどだ。
そこで付近の宿泊できる場所を検索しようとすると、いわゆるビジネスとして旅館・ホテルの斡旋をする「じゃらん」のような専門サイトのページばかりが出てくる。これは自分とこの契約ホテルしか出てこないうえに、検索ノミネートしてくる幅が広すぎる。
つまり、たとえで言うと、こちらは茨城の海岸のホテルを探そうとしているのに、箱根の山の中のホテルがお勧めですよ、と平気で言うようなものだ。およそ、人をバカにしておる。
不動産関係の検索にも似たようなことがあって、ストレートに物件に行き当たることは少なく、たいていはまずは不動産業者のページへどうぞと誘導されるが、そこに探している物件があるとは限らない。
さて、問題の「唐琴警鐘台」。
これが、Yahoo!で検索したところ、そのほとんどすべてが「唐琴警鐘台バス停下車徒歩5分」といった、不動産や施設の道しるべとして記載されたものだけ。それについてのまともな情報は、皆無だった。
「唐琴警鐘台」は、何に警鐘を鳴らそうとしているのだろうか。ナゾである。
この件について、問い合わせていた倉敷市役所児島支所から、返事とともに写真と所在図まで、送っていただいたので、それを追加しておこう。ただし、所在図は「バス停から北の山のほうに若干登ったところ」ということで。ありがとうございました。(2009/09/11追記)
「唐琴警鐘台とは,唐琴地区にある旧消防機庫の隣に設置された火の見櫓のことだそうです。
場所および写真を別添で送付させていただきますので,よろしくお願いします。児島支所総務課(09/09)」

やっぱり火の見やぐらだったんだ。それにしても、返事かきたこの日は09/09(救急の日)!? 関係ないですね。
▼国土地理院 「地理院地図」
34度28分1.93秒 133度51分34.06秒
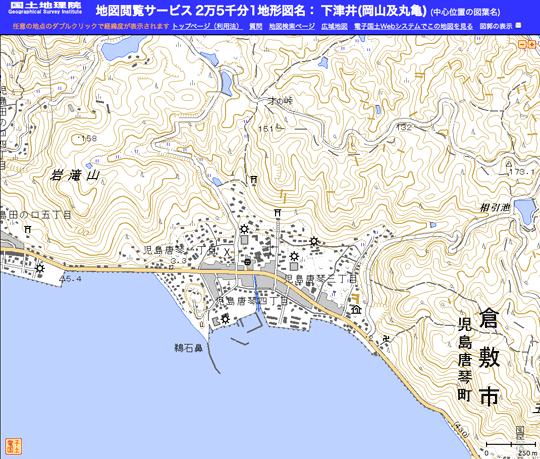
タグ:岡山県


 番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)
番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)





 2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
毎度、おのが無知をさらすやうだが、唐琴は初耳でござる。たしかに由緒いわくありげな地名で想像をかきたてるのう。
愚考するに──各地に大崎・長崎・黒崎が多い(データベース1)やうに、岬の名は外観・形状に由来するものが多い。とすれば、地形が唐琴に似ているといふのは上空からの目線ゆえ(比較的に新しい命名ならともかく)賛同しかねる。まず岬ありきではなく、児島付近に唐琴といふ地名がありそれが岬名になったのではないか。また地名の多くがさうであるやうに、古くから自然発生的に呼び慣わした“音”に唐琴の漢字を当てはめたのではないか。
いずれにせよ、中国版『怪盗ルパン』物語のごとき妄想がふくらむ地名「唐琴警鐘台」を究明せずに終わったのはまことに残念でござった。
by dotenoueno-okura (2009-09-03 10:52)
@いやいや、それはいささか違いまするな。上空からの目線というのは、飛行機がなくても、丘(警鐘台とか)に登る、山の上に登ることで地形観察は充分に可能でござる。
もちろん、地名には前から音があって、それを表わす漢字を当てはめたという場合も、多くありまするが、この場合は違う。
やはり「唐」に由来する何かがあって、ついた地名だと思われまするな。
「唐船」という名のついた岬は、いくつかあるが、それらも文字通りの事実を表現したと考えるほうが、よほど自然でありまするからな。
by dendenmushi (2009-09-05 06:18)
初めまして。この唐琴で生まれ育ち18歳まで過ごしました。今や離れてさらに18年・・・、子供の頃よく遊んでた場所なので、UPされてることがすごく嬉しいです!
さて唐琴の由来について。小学生の時先生から教わったのは、昔々中国が唐と呼ばれていた時代に唐から琴を持った女性がこの浜に流れ着き皆に琴の音色を聴かせたそうです。しばらくしてその人は亡くなり、惜しむかのように地名を唐琴としたそうです。
あと警鐘台ですが、火事があった時、実際に警報を出していたんですよ。この児島海岸部は特に乾燥していて私が小さい頃山火事は日常茶飯事のようでした。多い時は月2回ほど・・・!警鐘台から20mほど下ったところに駄菓子屋がある(今もあるかな?)んですが、そこでボヤがあった時も警鐘台はなってました。
土地が狭く道も狭いし児島中心部から外れているので今は人も減っていますが、瀬戸大橋が一望でき、海岸も近く、裏にすぐ山があって、景色の良いまちでした。
また訪れていただけることがあれば、今度は王子ヶ岳からの眺めも楽しんでください。2丁目の国道沿いに旅館あったけど無くなったのかな?? ではww
by 地元出身者 (2010-02-17 00:08)
あと管公にまつわるお話をもう一つ。
”菅原道真公が九州太宰府に左遷される途中、児島琴浦に泊まられた。村人は歓待し、夜明けの一番鶏が鳴くまでお引き留めする予定であった。しかし、どうしたことか、鶏が時刻を間違えて早く鳴いたので、お別れが早くなってしまった。それ以後、この村では鶏を飼わぬ風習が生まれ、この地に菅公を祀ることとなった。”
小さいころからこの地では”当然”のしきたりで”唐琴でニワトリ飼うと雷が落ちる”と言うと田の口住民からは笑われていました。児島では結構メジャーな言い伝えです!
by 地元出身者 (2010-02-17 00:35)
@地元出身者さん、ありがとうございます。なるほどね、やっぱりそういう伝説があったのですね。何かあるだろうと思って検索してみても、何も出てこなかったのは、要するにそれについて知っている人が少ない、知っていてもネットに書き込むような術も気もないという人が多い、ということなのでしょうか。
いずれにしても、おかげさまで、「唐琴」のナゾも解けました。
菅公さんの言い伝えもおもしろいですが、これは全国あちこちにある説話の類いに同パターンのものがおおくあるので、それを借りたつくり話っぽいですけどね。
でも、こういうことは、もっと伝えていく必要がありますね。
唐琴周辺は、ほんとに穏やかなきれいな海でした。王子ヶ岳の岩もなかなか興味深いものでした。
by dendenmushi (2010-02-17 07:05)