436 象の鼻=横浜市中区海岸通一丁目(神奈川県)大きく果てしなき「流れ」のなかの邂逅を… [岬めぐり]

もちろん、これを入れたのはシャレである。いくら「鼻」がついているとはいえ、岬としての名前ではない。「象の」と限定した「鼻」の形容ではあるが、出っ張っているから「鼻」がついたわけではなく、最初からその形が象の鼻に似ていたからついた名である。だから、「なんとかの鼻」という岬の呼名とは当然に異なる。第一、ここは突堤ではあっても、岬とはいえない。
しかし、それでも、形といい場所といい、これを特別に岬の仲間に加えることに、なんら不都合がない。それに、これでも入れておかないと横浜は“岬めぐり”からは完全に抜け落ちてしまう。
150年前に日米修好通商条約をはじめ5か国と条約を結び、戸数90戸程度の寒村だった横浜村を港として開港した。そのときに、まだ大きな船が横付けできる桟橋がなかったので、艀からの積荷の上げ下ろしのためにできた横浜港で最も古い二本の突堤のひとつがここであるという。横浜港の開港こそが、日本の「開国」でもあったわけだ。

見つかった古い石組みを整備した突堤に組み込み、新たな港ヨコハマの名所にすべく、周辺を「象の鼻パーク」として、6月2日の開港記念日に公開されることになった。
だいたい、横浜の人の多さは半端ではない。ただでさえ人が多いところへもってきて、折しも開国・開港150周年の祭りで盛り上がる横浜は、ここのところ人々が近郊近在から集ってきて、もう大変な人出人波である。
それもあらかじめ予想できたので、ここにはオープン前にわざわざ行って、まだ人が一人も入れない象の鼻の写真を撮ってきた。(こういう写真は、もう撮れませんぜ。…早朝とか行けば、そうでもないか。)
この俯瞰写真は、うまい具合にチャンスがあって、開港記念館前のビルの窓から撮ったので、ガラスの反射が避けられないが、もともときれいな写真や芸術的写真に熱を入れているわけではなく、単なるメモ代わりの写真なので、はっきり言って写っていればいい、撮れていればいいのだ。
それでも、人が溢れるときに行って、象の鼻を撮ったのか人の鼻を撮ったのかがわからないようなのは、とにかくいやだったのだ。こういうところにこだわるのも、へそまがりの面目である。
象の鼻のそばの大桟橋も、すっかりその面目を一新している。なにかどこかでトゲでも刺さりそうな感じもするが、広くて大きいウッドデッキはすばらしい。
それだけでなく、横浜のみなとみらい地区の再開発には、この付近の昔を少しでも知る者にとっては、その変貌ぶりに目を見張るばかりであろう。
現代の建築土木技術は、なんでもどんなことでもやってしまうのだなあ、と横浜の移り変わりも感心して見てきた。もちろん、再開発や公共施設の拡充は、住みやすい町をつくるうえからも欠かせない。
問題は、それがほんとうに必要かどうか、だけである。その点ではこういう公共スペースが中心の町づくりは、「アニメの殿堂」とやらいう特定の人間のためのハコモノとは異なり、素人の納得も得やすいのだろう。

50数年前に、とある田舎の高校生が修学旅行で、ここにやってきた。東京オリンピックのヨット会場にするため消されてしまうことになる磯浜に面した江ノ島の旅館に泊まり、鎌倉を七里ヶ浜の磯づたいに長谷の大仏、鶴ヶ岡八幡宮とめぐって松竹大船撮影所から横浜の大桟橋を経由して東京へ向ったのだ。そのときは、ポイントでは降りたもののバスで通り過ぎただけだったが、それから13年後には、彼が横須賀線(これも今年が開通120年だという)で、逗子=東京間を30数年にわたって毎日往復することになろうとは、その当時には想像できることではなかった。
なにか、急に個人的な感傷世界に入ってしまったように読まれてしまいそうだが、場所と時間と自分の、大きな「流れ」のなかの邂逅を考えている。
こういうことは、誰にでもあることだが、それも日頃はすっかり忘れている。しかし、たまにそれらを反芻してみると、『自分が生きていること・生かされていること』の意味を、わずかでもふと考えることにもなる。
横浜は、日本でいちばん最初に大きな時代の流れと、その変化に遭遇し、対応して生きてきた街である。
35度26分58.86秒 139度38分43.38秒
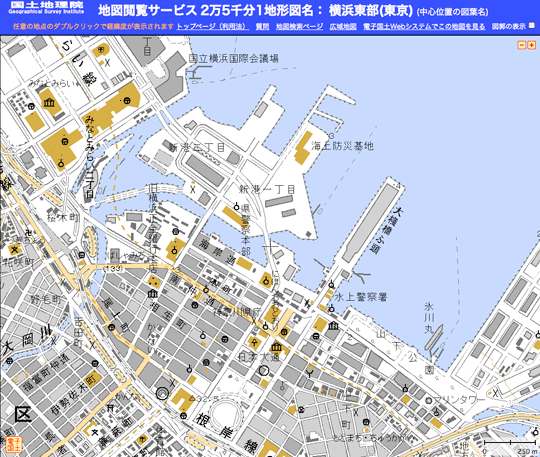


 番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)
番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)





 2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
コメント 0