382 住吉崎=和歌山市大川(和歌山県)泉州から境界を越えて「紀伊国」へ入って最初の岬がこれ [岬めぐり]
住吉神社のある岬のすぐ隣が住吉崎というのは、なにか関連があるのだろうか。住吉崎自体は、和歌山県最北の岬になるが、道路とその下の浜小屋のような青いシート以外に人工物はなにもない、周囲にも人の気配もないところだ。切り立つ崖の岬の先に、遠く山の影が見え隠れするのは、もちろん淡路島である。

大阪府との県境は、普通に考えれば高森山の山並みに沿って、西に真っすぐ延びていってもよさそうなものだが、大川という小さな集落とその周辺の山を、わざわざ和歌山県に取り込むためのように、北に折れ曲っている。

県境には、「紀伊国」と彫った大きくてかなり古そうな石標が立っているが、海岸のごみが気になる。ここから見る住吉崎の向こうに顔を出しているのは次の戎崎だろう。

紀伊国に入って、最初の集落である大川は、お寺と神社と漁港がある小さな川が一本流れ込んでいる谷間にある。海岸は、柚ノ浜という名前が残っているが、今では道路と護岸とに消されたか、あるいは地盤の沈下で消えたか、それとも満潮でかくれているだけなのか、浜らしいところは見えない。
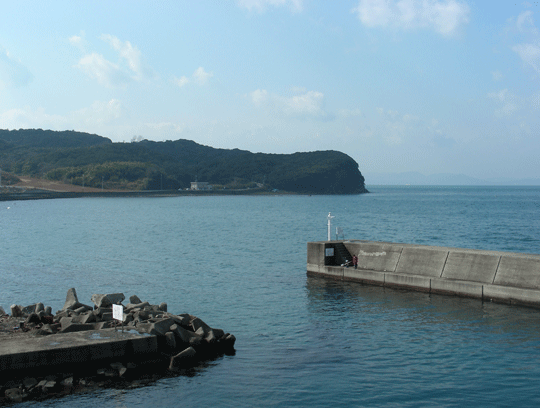

ただ、ところどころ浅瀬に岩の層が露出しているのは、和泉層群の地盤だろうか。和泉層群というのは、地質学では有名な中生代白亜紀末の地層で、中央構造線に沿って長く続いている。アンモナイトの化石などが見つかることもある地層だが、柚ノ浜もその一部だったのだろう。
北東を向けば、明神崎が見え、西を向けば住吉崎がだんだん大きくなってくる。
日本中隅々に至るまでも、道路工事はきめ細かに行なわれている。なかにはムダや汚職や政治家の口出しや不明朗な入札などもつきものらしいのが問題だが、確かに道路だけはどんな田舎に行っても、未舗装の道は滅多にない。これはこの国の行政能力の証しのひとつともいえる。とにかく、人がいないところでも、道路だけはある。

工事現場の先へ真っすぐ行くと、大川トンネルが、約1キロ続いて山の中を通り抜けている。加太へ抜けるには、これがいちばんの近道だが、そっちへは行かない。どう考えても、1キロも排気ガスの穴の中を歩くのはご免だ。
地図で見ると、峠越えの旧道があるので、登りにはなるがそっちの道を行ったほうがはるかにいいし、それに戎崎もチェックする必要があるが、トンネルを行ったのでは、それも確認できない。



住吉崎の手前から、峠に向かう旧道が上って行くが、なんとしっかり通せんぼがしてある。その説明やらなんやら、いろいろ注意書きが示されているが、それによると、路面が傷んでいて通行の危険があるから当分の間、車両の通行は禁ずる、というのである。

人の通行までは禁じていないので、柵横の隙間から入って歩くことができる。住吉崎に別れを告げ、これからいよいよ大川峠越えに向かう。
▼国土地理院 「地理院地図」
34度18分28.46秒 135度4分46.82秒
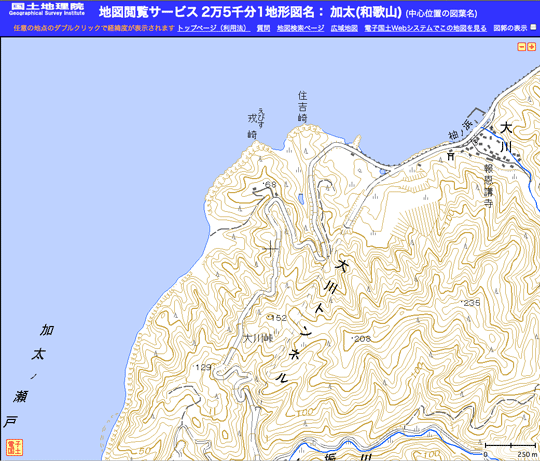
 近畿地方(2009/01/23 訪問)
近畿地方(2009/01/23 訪問)




大阪府との県境は、普通に考えれば高森山の山並みに沿って、西に真っすぐ延びていってもよさそうなものだが、大川という小さな集落とその周辺の山を、わざわざ和歌山県に取り込むためのように、北に折れ曲っている。

県境には、「紀伊国」と彫った大きくてかなり古そうな石標が立っているが、海岸のごみが気になる。ここから見る住吉崎の向こうに顔を出しているのは次の戎崎だろう。

紀伊国に入って、最初の集落である大川は、お寺と神社と漁港がある小さな川が一本流れ込んでいる谷間にある。海岸は、柚ノ浜という名前が残っているが、今では道路と護岸とに消されたか、あるいは地盤の沈下で消えたか、それとも満潮でかくれているだけなのか、浜らしいところは見えない。
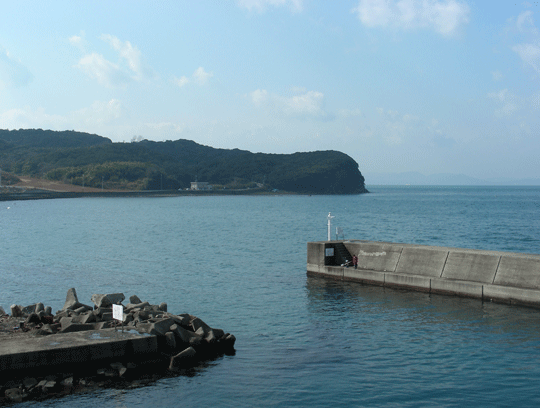

ただ、ところどころ浅瀬に岩の層が露出しているのは、和泉層群の地盤だろうか。和泉層群というのは、地質学では有名な中生代白亜紀末の地層で、中央構造線に沿って長く続いている。アンモナイトの化石などが見つかることもある地層だが、柚ノ浜もその一部だったのだろう。
北東を向けば、明神崎が見え、西を向けば住吉崎がだんだん大きくなってくる。
日本中隅々に至るまでも、道路工事はきめ細かに行なわれている。なかにはムダや汚職や政治家の口出しや不明朗な入札などもつきものらしいのが問題だが、確かに道路だけはどんな田舎に行っても、未舗装の道は滅多にない。これはこの国の行政能力の証しのひとつともいえる。とにかく、人がいないところでも、道路だけはある。

工事現場の先へ真っすぐ行くと、大川トンネルが、約1キロ続いて山の中を通り抜けている。加太へ抜けるには、これがいちばんの近道だが、そっちへは行かない。どう考えても、1キロも排気ガスの穴の中を歩くのはご免だ。
地図で見ると、峠越えの旧道があるので、登りにはなるがそっちの道を行ったほうがはるかにいいし、それに戎崎もチェックする必要があるが、トンネルを行ったのでは、それも確認できない。



住吉崎の手前から、峠に向かう旧道が上って行くが、なんとしっかり通せんぼがしてある。その説明やらなんやら、いろいろ注意書きが示されているが、それによると、路面が傷んでいて通行の危険があるから当分の間、車両の通行は禁ずる、というのである。

人の通行までは禁じていないので、柵横の隙間から入って歩くことができる。住吉崎に別れを告げ、これからいよいよ大川峠越えに向かう。
▼国土地理院 「地理院地図」
34度18分28.46秒 135度4分46.82秒
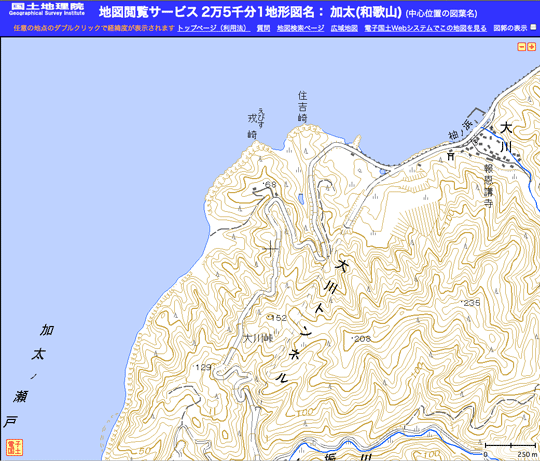
タグ:和歌山県


 番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)
番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)





 2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
さすが紀伊国、天候にも恵まれて明るい光景ですね。自殺や殺人事件のロケーションには向きそうにない。
和泉層群ねえ──いい学習をしました。三重県の先っぽ(賢島あたり)に似たような海岸線があったような気がするのですが、地理学的には同じですかね。
「加太」で「こうじ」を連想しました。関西本線にこういう駅があったと思っているので、ここで出会うとは意外でした。
by knaito57 (2009-02-23 18:47)
@おや? 出不精で、関西に縁のないはずのknaito57さんから、関西本線の「加太」という駅の名を聞こうとは思いませんでしたよ。
ありますねえ、名古屋からだと亀山・関・加太・柘植と続き、ここで草津へ行く線と分かれます。
和歌山の加太は「かだ」と読みます。ここはJRは通っていなくて、南海電車だけなので、重複はなしと判断されたのでしょうね。
関西では、ここらは結構おいしい魚を食べられると有名なのです。
by dendenmushi (2009-02-25 07:56)
2014.7.10日。資料確認で何気なく貴殿のブログを拝読。僕は、幼少時、大川村の祖母屋敷に預けられ、戦争時は、七歳で文校通い。このあたりは、「孫たちへの証言13集」新風書房に収録。小・中・高・大学と夏休みは、毎年1か月逗留。村が権力者たちの汚職犠牲になるまで、別世界の美しい村で、25m前後の磯馴松(そなれまつ)が、小島から、行き止まりの大川村八幡神社下まで百本以上が海岸を護っていたのです。かつて若き法然の漂着、紀伊国屋文左衛門、皇女和宮御忍び行幸など、怪奇と幻想の隠れ村。小説のネタがゴロゴロ潜んでいる限界村かと。ご縁があれば、再見したいと思います。懐かしく悲しく拝読しました。
by 小椋 道生 (2014-07-10 14:10)
@小椋さん、コメントありがとうございました。大川村の思い出をいっぱいかかえておられるのですね。
通りすがりのでんでんむしも、大川の海岸はよく覚えています。そうですか、磯馴松…ですか。なにか、それも曰くありげですね。
その松が、いまも残っていれば…というようなところはたくさんありますね。
大川の周辺は、遊漁施設がたくさんあったようですが、大川峠越もなかなか印象深いものでした。
by dendenmushi (2014-07-11 06:10)