326 矢田新出崎=七尾市矢田新町(石川県)埠頭に岬の名がつくのはめずらしいかも [岬めぐり]
鹿渡島からの帰りのバスは、七尾南湾に沿って南下していくが、ぼちぼち人家も増えてくるかという辺りで火力発電所の前を通る。発電所は湾の海が埋め立てられたようにそこだけが出っ張っているが、ここには赤崎という字名もあったらしい。これも、現在の住居表示には表われてこない地名である。すると、ここにも昔はそういう岬があり、今はそれが火力発電所で覆われてしまっている、と推測することは容易であろう。
発電所の南には貯木場が続き、ここからおよそ6キロに渡って、七尾港の埠頭や岸壁が続いている。なにしろ内湾のことで、どんなに荒れたとしても、高い堤防や防波堤は必要としないので、港は開放的である。
途中バスは「浜万行」というバス停を通るので、そこで降りる。来るときにもその名前を聞いたときに、頭の隅でなにやらが刺激され聞き覚えのあるように思ったのだが、どうしても思い出せない。確かなにかあったはずだと、とりあえず帰り道では降りてみたのだが、そこは殺風景な国道160号線が通り、ひっきりなしに車が流れている街の中で、気になる記憶を呼び覚ましてくれる何ものもなかった。


結局のところ余計に歩くことになってしまっただけだったが、矢田新町で海に向かう道に折れ、もはや夕暮れに近い淋しい倉庫などの間を行くと、その突端の突き当たりが、矢田新出崎になる。そこは二本の埠頭が突き出しているところだった。
だいたいにおいて、埠頭はその気になれば割りとずんずんとどこまでも入っていけたりするものだが、ここはそういうわけにはいかない。
なにしろ厳重にフェンスが巡らせてあり、頑丈な鍵までついていて、おまけに恐ろしげな警告文まで掲げてある。
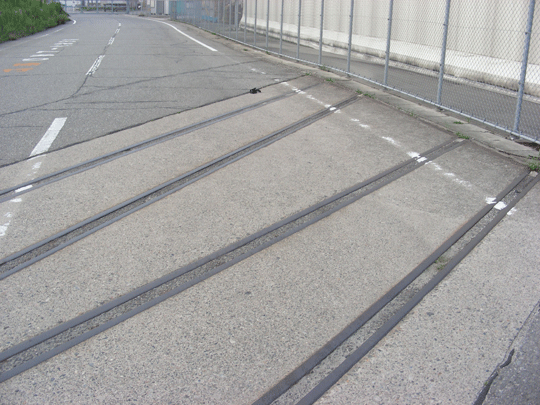
古いレールが、道路に埋め込まれたままになっているのをみると、かつては引き込み線があり、相応の働きをしていたものだろう。
この埠頭には、海上保安庁や国交省関連の役所の出先機関も集っていて、それらの建物が目立っているが、静まり返っているのでもう仕事は終えたのだろうか。
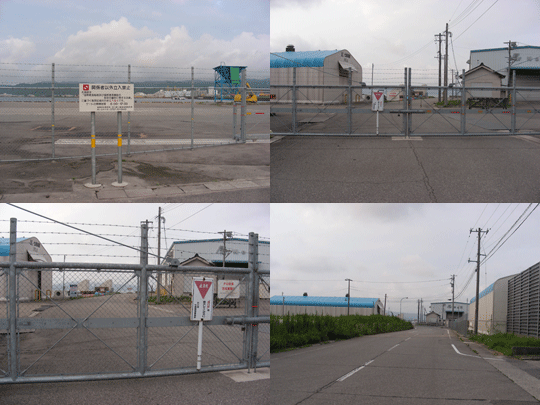
夕暮れの埠頭くらい淋しいものはない。
帰ってきてから、浜万行について調べてみると、そこからもう少し内陸に入った万行町で、5〜6年前に遺跡が発見されたことがあるという。どうも、気になっていたのはそのわずかな記憶の断片が、刺激されたためだったらしい。
それは3世紀末から4世紀初めにかけての古墳時代前期のもので、他に例をみない巨大な高床倉庫群の遺跡だったらしい。
古墳時代前期といえば、ちょうど大和政権も始まった頃である。けれども、ここは畿内からは遠く離れた場所である。そのため、この独特な倉庫群は、大和朝廷とは無関係に存在していたとみるほうが妥当だろう。
遺跡は小高い丘にあり、その昔は倉庫群のすぐ下までが海だったのだろう。つまり、古墳時代の埠頭だったのかもしれない。ということは、波も静かな七尾湾では、水運もかなり発達していたのだろう。
こういう想像は、学問的に言うと物証がない限り認められないのだが、シロウトが空想の羽を広げる分には、なかなか楽しい。だが、それも長く続かないのが少し淋しい。
▼国土地理院 「地理院地図」
37度3分6.99秒 136度58分45.86秒
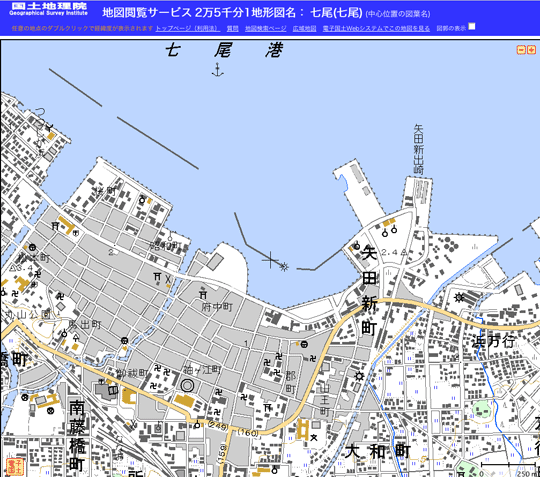
 北越地方(2008/09/06 訪問)
北越地方(2008/09/06 訪問)


発電所の南には貯木場が続き、ここからおよそ6キロに渡って、七尾港の埠頭や岸壁が続いている。なにしろ内湾のことで、どんなに荒れたとしても、高い堤防や防波堤は必要としないので、港は開放的である。
途中バスは「浜万行」というバス停を通るので、そこで降りる。来るときにもその名前を聞いたときに、頭の隅でなにやらが刺激され聞き覚えのあるように思ったのだが、どうしても思い出せない。確かなにかあったはずだと、とりあえず帰り道では降りてみたのだが、そこは殺風景な国道160号線が通り、ひっきりなしに車が流れている街の中で、気になる記憶を呼び覚ましてくれる何ものもなかった。


結局のところ余計に歩くことになってしまっただけだったが、矢田新町で海に向かう道に折れ、もはや夕暮れに近い淋しい倉庫などの間を行くと、その突端の突き当たりが、矢田新出崎になる。そこは二本の埠頭が突き出しているところだった。
だいたいにおいて、埠頭はその気になれば割りとずんずんとどこまでも入っていけたりするものだが、ここはそういうわけにはいかない。
なにしろ厳重にフェンスが巡らせてあり、頑丈な鍵までついていて、おまけに恐ろしげな警告文まで掲げてある。
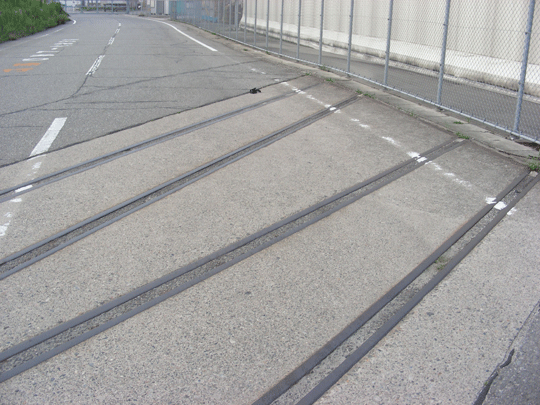
古いレールが、道路に埋め込まれたままになっているのをみると、かつては引き込み線があり、相応の働きをしていたものだろう。
この埠頭には、海上保安庁や国交省関連の役所の出先機関も集っていて、それらの建物が目立っているが、静まり返っているのでもう仕事は終えたのだろうか。
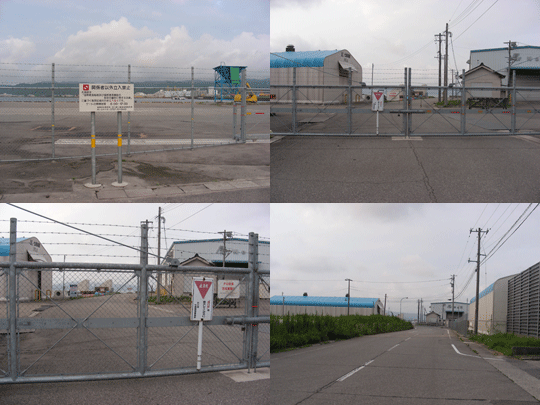
夕暮れの埠頭くらい淋しいものはない。
帰ってきてから、浜万行について調べてみると、そこからもう少し内陸に入った万行町で、5〜6年前に遺跡が発見されたことがあるという。どうも、気になっていたのはそのわずかな記憶の断片が、刺激されたためだったらしい。
それは3世紀末から4世紀初めにかけての古墳時代前期のもので、他に例をみない巨大な高床倉庫群の遺跡だったらしい。
古墳時代前期といえば、ちょうど大和政権も始まった頃である。けれども、ここは畿内からは遠く離れた場所である。そのため、この独特な倉庫群は、大和朝廷とは無関係に存在していたとみるほうが妥当だろう。
遺跡は小高い丘にあり、その昔は倉庫群のすぐ下までが海だったのだろう。つまり、古墳時代の埠頭だったのかもしれない。ということは、波も静かな七尾湾では、水運もかなり発達していたのだろう。
こういう想像は、学問的に言うと物証がない限り認められないのだが、シロウトが空想の羽を広げる分には、なかなか楽しい。だが、それも長く続かないのが少し淋しい。
▼国土地理院 「地理院地図」
37度3分6.99秒 136度58分45.86秒
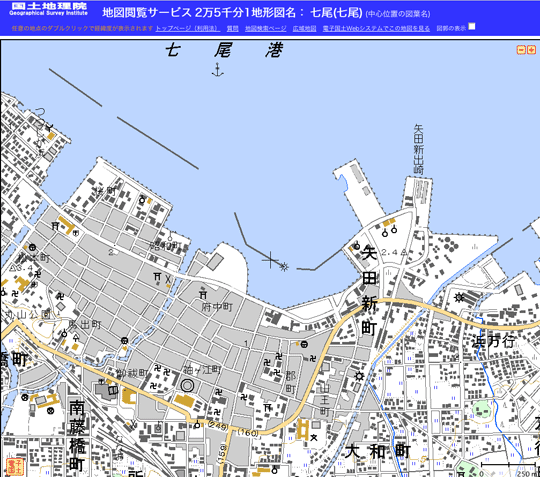
タグ:石川県


 番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)
番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)





 2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
そりゃ間違いないですよ、ワトスン君。おだやかな内湾を見下ろす小高い丘といえば、古代の人々が好んだ立地ですからな。森が近く海の幸にめぐまれ、もちろん川もあるはず──舟はくり抜きの丸木舟でしょうな。
でんでんむしさんのような彷徨癖のない拙者は昨秋、ルパン物を読み返したところからはずみがついて丸1年間ミステリー漬け。古典・名作といわれるものはあらかた読んで、近ごろは図書館から借りてきたハヤカワミステリ(縦長で木口の黄色いやつ)を積み上げて読み崩してます。毎日、自殺や連続殺人が起こり、名探偵やタフな警部が活躍するのを読むと、このジャンルはルブランやドイルが想像もしなかったほど多彩な発展をとげたものだと思います。
by knaito57 (2008-10-16 16:06)
@ワトスン君は、いちおうホームズの活躍を記録するという役目を負っているのだから、まあ許せるが、ポアロにいつもくっついているヘイスティングの役どころ(けっこうオバカ)は、なかなか悩ましい。
ハヤカワミステリは、当時から新刊本の中でも比較的高い本だったので、文庫本のほうをよく買っていた。
もっとも、今でも早川書房の本は他に比べて高いように思う。
そこで、もっぱら図書館で読むことにしているが、最近発見したのが「ハヤカワSFシリーズJコレクション」。
日本のSFの新人発掘に努力しているらしい。これが縦長の小口の黄色いシリーズを意識したような判型なのだ。
by dendenmushi (2008-10-18 09:02)