番外:水俣病資料館=水俣市明神町(熊本県)国は見えんじゃったと水俣で… [番外]
水俣の町の中心部は、三方を山や丘で囲まれた水俣川の河口に展開している。その南西の丘よりにチッソの工場がある。その前身を辿れば、明治の終わり頃まで遡るが、この場所に工場ができたのは大正にはいってからのことだ。今に残る野口町という町名は、この会社の創業者の名前によるものだろう。
工場の南には丘が伸びていて、町の中心とさらに南側に続く岬の間に点在する漁村とを隔離しているかのようでもある。その岡の西の端が明神崎で、そこに水俣市立の水俣病資料館がある。そのそばには水俣メモリアルという祈りと誓いの祈念の場所がある。
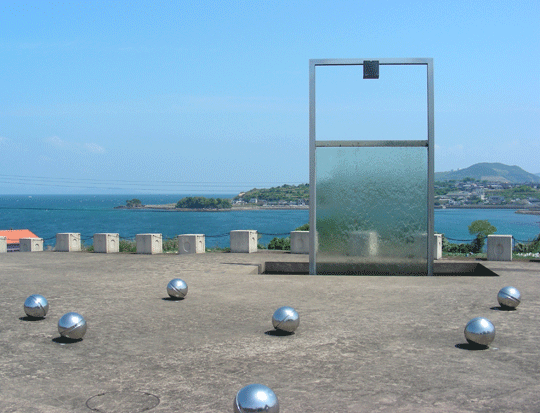



buzzmapが採用しているZENRINの地図では、熊本県環境センターという表示はあっても、水俣病資料館の存在は無視されている。こういう地図や案内は、ほかにもある。
図体だけは大きなこの環境センターの建物は、なぜここにあるのか、市に対抗して無理に県もなんか建てなきゃというので建てたみたいな、あまり意味のない展示がおざなりにしてある、という印象しかなかった。
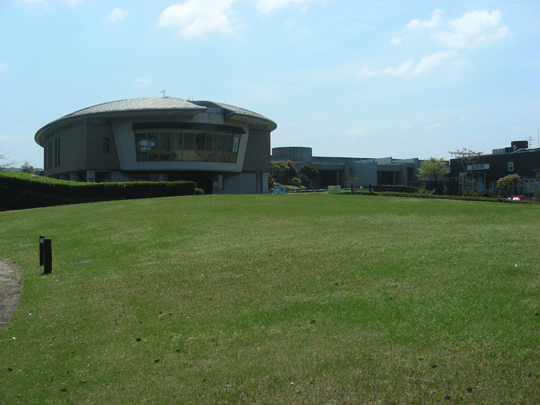
ZENRINの地図で見事に無視されている水俣病資料館は、この歴史について無知な人間にとっては、衝撃的である。
見る人によって、その受け止め方はさまざまだろうが、でんでんむしにとって最も衝撃だったのは、この問題に対して会社がとってきた姿勢と、当時の市や県やそして国がとってきた、あるいはとってこなかった対策についてである。
会社とはなにか、行政とはかくもだらしなく無策なものか、国とは政治とはいったいなんなのか、ということをつくづく考えさせる。
水俣で“原因不明”の奇病が認められたのは、公式には1956(昭和31)年のことだが、チッソが百間川から水俣湾に垂れ流していたメチル水銀を含む工場排水が止められたのは、それから12年も後のことだった。政府が水俣病が公害病であることを認めるまでに、どうしてそんなに長い時間がかかったのだろうか。


その間にも、多くの悲しい出来事が、ヘドロとともに次々と堆積していった。
いわゆる企業城下町の典型で、国鉄が鹿児島本線を敷き駅をつくるときにも、その場所は町の中心ではなく、迷わず会社の正門前につくった。被害がではじめた当時の市長さえもがチッソの出身でもある水俣という町の人々が、その被害者に当初から理解を示し同情的であったわけでもなく、“数百人の漁民のために何万という市民が犠牲になれというのか”という、ありがちな流れに集約されていったこともそうだったろう。歩いてみれば道の上をなにやら知れぬパイプがまたいでいるこの明神・汐見の丘はそう高くはないけれども、当時は被害者が多くでた漁村を遠く隔絶する境でもあった。

公害の原点とされる水俣病は、日本という国と日本人のもつどうしようもない情けなさをも凝縮しているように思える。もっと悲しいことは、役人というものは、過去にいくつも参考にすべき事例があっても、決して歴史から教訓を学び取ろうとはせず、同じような過ちを繰り返しているのではないだろうか、という疑問がたびたび頭をもたげるようなことが、いっこうになくならないことである。
資料館にあった展示のひとつに、こんなことばがあった。
「東京まで行ってみたばってん日本ちゅう国はみえんとじゃった。探して探して往ったがな。東京タワーにも上って、宮城にも参ってみたが、どこにも国は見えんじゃった。」

今、資料館の横から水俣の海を眺めれば、ヘドロ処理で埋立てた公園が広がっているが、これはそれが心配されて反対運動もあった二次被害を出さずに海底に溜まっていたヘドロを処理したという点で、画期的なものであったらしい。
水俣の町は、公害の町の歴史を乗り越えて環境への取り組みに目覚めたようで、新たな町づくりにも懸命なようだ。しかし、補償問題はいまだに全面解決には至っていない。
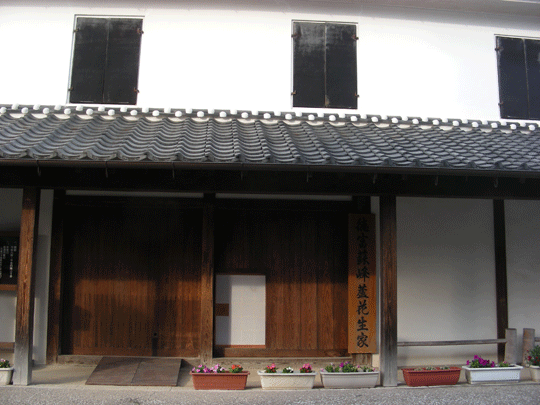

ちょうどこの町に滞在していた2日間、三社祭りとかで通りには出店屋台が並び、イベントが行なわれていた。どこに神社があるのだろうと、町を歩いてみたが、どこにもそれらしいものは見つけられず、その代わりに徳富蘇峰・蘆花の生家を発見した。おやこれはまた、意外なところで蘆花さんに。でんでんむしが住民登録している神奈川県逗子市は、徳富蘆花が住んでいたところなのである。
徳富兄弟は水俣にとっても、郷土の偉人であった。蘇峰は、郷土の小学校の校歌を依頼されて、こう謳った。
「矢筈の山の空の色 月の浦わの波の音 清くさやけき水俣の 吾らは行かん人の道」
人の道とは、まこと険しいものである。
▼国土地理院 「地理院地図」
32度12分13.21秒 130度22分29.82秒
 九州地方(2008/04/19 訪問)
九州地方(2008/04/19 訪問)


工場の南には丘が伸びていて、町の中心とさらに南側に続く岬の間に点在する漁村とを隔離しているかのようでもある。その岡の西の端が明神崎で、そこに水俣市立の水俣病資料館がある。そのそばには水俣メモリアルという祈りと誓いの祈念の場所がある。
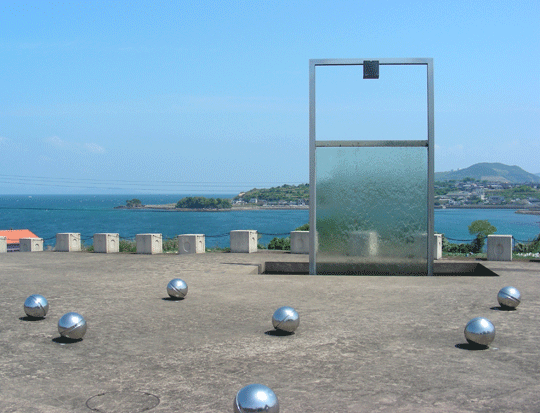



buzzmapが採用しているZENRINの地図では、熊本県環境センターという表示はあっても、水俣病資料館の存在は無視されている。こういう地図や案内は、ほかにもある。
図体だけは大きなこの環境センターの建物は、なぜここにあるのか、市に対抗して無理に県もなんか建てなきゃというので建てたみたいな、あまり意味のない展示がおざなりにしてある、という印象しかなかった。
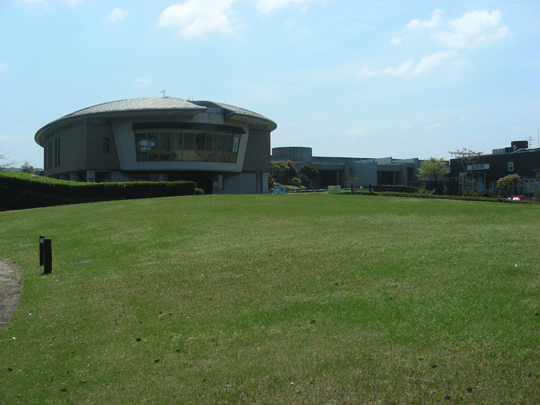
ZENRINの地図で見事に無視されている水俣病資料館は、この歴史について無知な人間にとっては、衝撃的である。
見る人によって、その受け止め方はさまざまだろうが、でんでんむしにとって最も衝撃だったのは、この問題に対して会社がとってきた姿勢と、当時の市や県やそして国がとってきた、あるいはとってこなかった対策についてである。
会社とはなにか、行政とはかくもだらしなく無策なものか、国とは政治とはいったいなんなのか、ということをつくづく考えさせる。
水俣で“原因不明”の奇病が認められたのは、公式には1956(昭和31)年のことだが、チッソが百間川から水俣湾に垂れ流していたメチル水銀を含む工場排水が止められたのは、それから12年も後のことだった。政府が水俣病が公害病であることを認めるまでに、どうしてそんなに長い時間がかかったのだろうか。


その間にも、多くの悲しい出来事が、ヘドロとともに次々と堆積していった。
いわゆる企業城下町の典型で、国鉄が鹿児島本線を敷き駅をつくるときにも、その場所は町の中心ではなく、迷わず会社の正門前につくった。被害がではじめた当時の市長さえもがチッソの出身でもある水俣という町の人々が、その被害者に当初から理解を示し同情的であったわけでもなく、“数百人の漁民のために何万という市民が犠牲になれというのか”という、ありがちな流れに集約されていったこともそうだったろう。歩いてみれば道の上をなにやら知れぬパイプがまたいでいるこの明神・汐見の丘はそう高くはないけれども、当時は被害者が多くでた漁村を遠く隔絶する境でもあった。

公害の原点とされる水俣病は、日本という国と日本人のもつどうしようもない情けなさをも凝縮しているように思える。もっと悲しいことは、役人というものは、過去にいくつも参考にすべき事例があっても、決して歴史から教訓を学び取ろうとはせず、同じような過ちを繰り返しているのではないだろうか、という疑問がたびたび頭をもたげるようなことが、いっこうになくならないことである。
資料館にあった展示のひとつに、こんなことばがあった。
「東京まで行ってみたばってん日本ちゅう国はみえんとじゃった。探して探して往ったがな。東京タワーにも上って、宮城にも参ってみたが、どこにも国は見えんじゃった。」

今、資料館の横から水俣の海を眺めれば、ヘドロ処理で埋立てた公園が広がっているが、これはそれが心配されて反対運動もあった二次被害を出さずに海底に溜まっていたヘドロを処理したという点で、画期的なものであったらしい。
水俣の町は、公害の町の歴史を乗り越えて環境への取り組みに目覚めたようで、新たな町づくりにも懸命なようだ。しかし、補償問題はいまだに全面解決には至っていない。
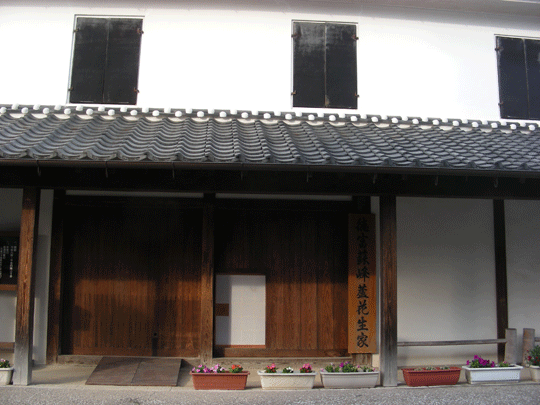

ちょうどこの町に滞在していた2日間、三社祭りとかで通りには出店屋台が並び、イベントが行なわれていた。どこに神社があるのだろうと、町を歩いてみたが、どこにもそれらしいものは見つけられず、その代わりに徳富蘇峰・蘆花の生家を発見した。おやこれはまた、意外なところで蘆花さんに。でんでんむしが住民登録している神奈川県逗子市は、徳富蘆花が住んでいたところなのである。
徳富兄弟は水俣にとっても、郷土の偉人であった。蘇峰は、郷土の小学校の校歌を依頼されて、こう謳った。
「矢筈の山の空の色 月の浦わの波の音 清くさやけき水俣の 吾らは行かん人の道」
人の道とは、まこと険しいものである。
▼国土地理院 「地理院地図」
32度12分13.21秒 130度22分29.82秒
タグ:熊本県


 番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)
番外:大津波が襲った東日本太平洋沿岸の岬に思いを込めて(『岬めぐり』大津波以前から既に掲載していた分のリスト)





 2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
2009年末から2011年初にかけて、So-netブログについてこんなことを考えて問題提起をしていた。その後も、状況はいっこうに変わってはいない。記録のため、「So-netブログのここがヘン」などと観察研究記録、地域ブログの定点観測をまとめ残す。
“企業城下町”の光と影(功と罪)はいろいろですが、大企業に無縁でそういう土地に住んだこともない拙者などは昔から羨望と胡散臭さを感じていました。そして隠居暮らしとなってからは後者のほうばかりがクローズアップしてきます。
企業と地域の持ちつ持たれつ関係が生んだもの、会社のためになされた犯罪、責任感なき公務員……曲がりなりにもそれで今日の日本があるともいえる。しかし、今日なお各国各地にある“垂れ流し”の現実を考えると、経済活動の“負”の面に目を向けないわけにいかない。岬めぐりはいろんなことを考えさせますね。
by knaito57 (2008-06-16 10:03)
@会社の幹部達に対して被害者がこの排水を飲んでみろ、奥さんにも飲んでもらおうと迫った、と伝えられています。
日本の会社というのは、妙なところである種の共通点がありますよね。
いちばんいけないのが、異論を排除することで、結局一番上のひとりが間違っていれば、誰もそれを修正できない…。
by dendenmushi (2008-06-17 07:05)